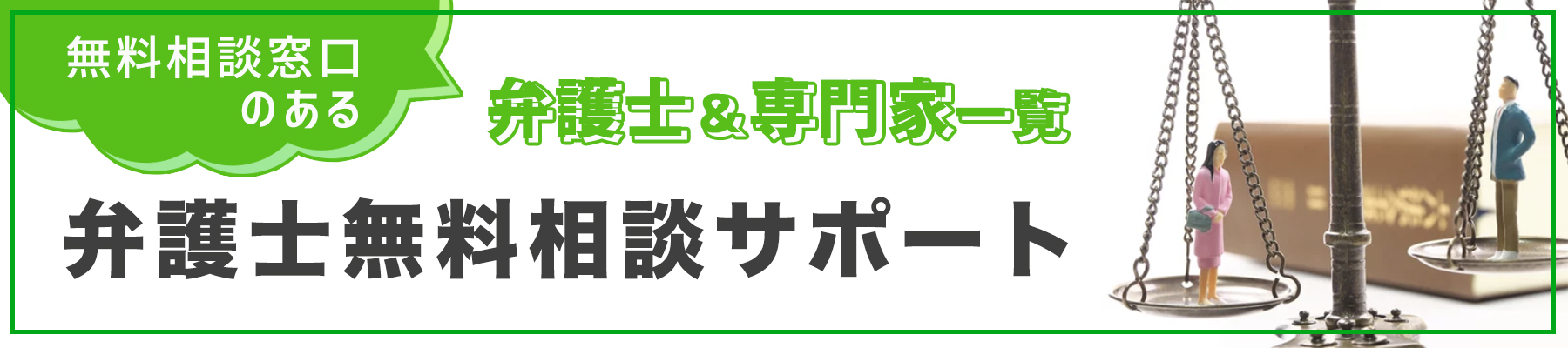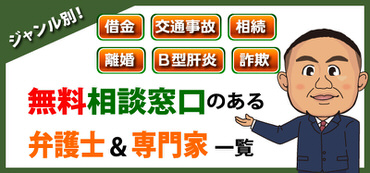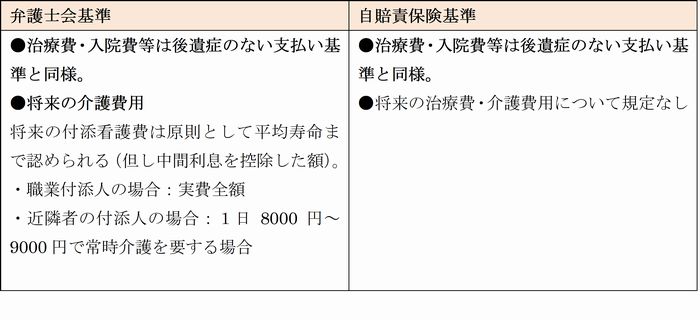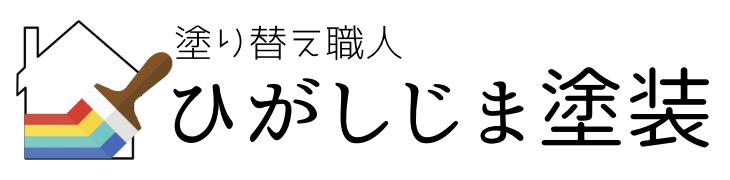�����k�����X�^�[�g����������̂��H
���Â��K�v�ȃP�[�X�����Q���c��P�[�X�ł́A���k���͎��̒���ɍs�����Ƃ͂���܂���B
���̌�A���@�E�ʉ@���I������^�C�~���O�A�܂��́A��t���u����ȏ��w�I�ɉ������߂Ȃ��v�Ɣ��f���Ď��Â��X�g�b�v�����^�C�~���O��������n�߂܂��B
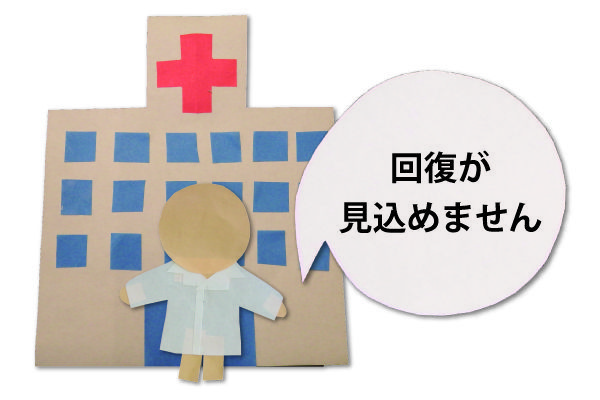
�������A��t���u����ȏ��w�I�ɉ������߂Ȃ��v�Ɣ��f�����ꍇ�ɂ́A����Q�ɂ��Ēm���Ă����Ȃ��Ă͂����܂���B
���ǂ��c��ꍇ�̎��k�ɂ��ďڂ����������Ă����܂��B
1. ���ǂƂ͈قȂ����Q�`���ǂ��c���������ł͔�������Ȃ�
���Â��Ă����炸�A�c���Ă��܂��Ǐ�̂��Ƃ��u�����v�ƌ����܂��B
�����āA��ʎ��̂ł́A���Â����Ă����S�Ɋ��������̂ɏ�Q���c�邱�Ƃ��悭����܂��B
���ǂ��c�����ꍇ�ɂ͎��k���͂ǂ��Ȃ�̂��H�ɂ��ẮA�����z�ɑ傫�ȍ����ł�|�C���g������܂��B
����Q�����ł��B
�u����Q�v�Ƃ��ē����F�肳���A���Q�����z�̎Z��Ɋ܂܂�Ă��܂��B
�P�Ɏ����Ō��ǂ��c�����Ǝ咣���Ă���������܂���B
���̂��߁A��t����������߂Ȃ��ƌ���ꂽ�ꍇ�ɂ́A����Q�̔F��ɂ��Č������Ă��������B
1-1 ���ǂ��c��ꍇ�͎��k������O�ɂ�邱�Ƃ�����`�f�f���̍쐬�ƔF��
��t�Ɂu����Q�f�f���v�̍쐬�����肢���܂��傤�B
�f�f���̓��e�͏d�v�ł��B
�f�f���̓��e�ɂ���āA�Ǐ���Q�ʓ����\�̉����ɊY������̂����f����܂��B
�ꍇ�ɂ���ẮA��ԒႢ�����ɂ����F�肳��Ȃ����Ƃ�����܂��B
�����F����s���̂͑��Q�ی������Z�o�@�\�̒����������ƂȂ�܂��B
�F��́A���ނ����̐R���Ō��܂�̂��ʏ�ł�����A��t����������Q�f�f�����ƂĂ��d�v�ɂȂ�̂ł��B
��t�ɂ͋�̓I�ȏǏ��`���A�ڍׂȏǏ��f�f���ɏ����Ă��炢�܂��傤�B
1-2 ����Q�̓����Ƃ́H�����\���牽���ɂȂ�̂��m�F���Ă�����
����Q�̓����͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��H
���L�̕\���Q�l�ɁA�����̏Ǐ����̌���Q�ɓ��Ă͂܂�̂��H�m�F���Ă����܂��傤�I
�u����Q�ʓ����\�E�J���\�͑r�����iH22.6.10�ȍ~�����������̂ɓK�p�j�v
�Q�l�F����Q�̓����y�ь��x�z�`���y��ʏ�
2. ���ǂ��c��ꍇ�ɂ͂ǂ�ȑ��Q�������ł���́H�傫��3����
�����������e�́A�傫��������Ɖ��L�̂R���ڂɂȂ�܂��B
- �ϋɑ��Q
- ���ɑ��Q�E�편���v
- �Ԏӗ��i���ʉ@�Ԏӗ��A����Q�Ԏӗ��j
�Ȃ��A���ǂ��c��Ȃ��l�g���̂Ƃ̈Ⴂ�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
�����̉�엿���v���X�����i�A���A�����ӊ�ł͋K��͂Ȃ��j
�편���v���v���X�����
���ǂɂ��Ԏӗ����v���X�����
3. ��ɂ���Ď�����z���Ⴄ�`�����ӊ�ƕٌ�m�����r
�����z���Z�o���邽�߂̊�ɂ́A�����ӕی���A�C�ӕی���A�ٌ�m��������܂��B
���̂��߁A��������Q���c�����P�[�X�Ŕ�r����ƁA��ɂ���Đ������z�ɈႢ���o�Ă��܂��B
�����ł͎����ӊ�ƕٌ�m�����ɏo���܂��B
������Q���c��ꍇ�̏��Q���̂̎x�������
�����@�{�s�ߕʕ\�T�A�U
�Q�l�F�����ԑ��Q�����ӔC�ی��̕ی������y�ю����ԑ��Q�����ӔC���ς̋��ϋ����̎x����`���y��ʏ�
�ٌ�m��̕����������炦�邱�Ƃ�������܂��B
����Q�����Ƃ��̈Ԏӗ����݂�Ɣ{�ȏ�ł��B
����Q����������ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�Ɉ˗����Ď��k���͍s���ׂ��ł��B
4. ���k���̃|�C���g�I�ٌ�m�Ɉ˗����ĕٌ�m���Ő�������������
����Q�̏ꍇ���ʏ�̏��Q���̂Ɠ��l�ŁA�ی���Ђ���Ƃ���x������ٌ͕�m�����Ⴂ���̂ł��B
���݂ɁA�ٌ�m���i�ٔ�����j�ł̐����ٌ͕�m�����A�܂��͍ٔ��ƂȂ����ꍇ�ɂ̂݉\�ƂȂ�܂��B
�����ł��ٌ�m���ɋ߂Â��邽�߂ɁA�܂��͈�x�����̏ꍇ�̔����z��������ɂȂ邩���v�Z���Ă݂�Ƃ����ł��傤�B
���̂����Ō����J�n���Ă݂ĉ������B
�������A����Q�̏ꍇ�́A�v�Z�����G�����z�ƂȂ�܂��B
�����ł́A�v�Z���������Ƃ������������A�ٌ�m�Ɉ˗����������������Ⴂ�܂��B
����Q���F�肳��Ă���ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�Ɉ˗������ق����茳�ɓ��邨���������Ȃ邽�߁A�ٌ�m��p�̐S�z�͕K�v�Ȃ��ł��傤�B
�܂��͔�p�̂��Ƃ��܂߂ĕٌ�m�ɑ��k���鎖�������߂��܂��B
5. ����Q�̏ꍇ�̎��ۂ̑��Q�z�́H�`�v�Z��
�ł́A���ۂɃV���~���[�V�������Ă݂܂��傤�B
�@�ϋɑ��Q�{�A���ɑ��Q�i�편���v�܂ށj�{�B�Ԏӗ��i���ʉ@&���ǁj�~�i100-�ߎ������j��100
���၄����Q�����鏝�Q���́i�ٌ�m���j
����
�ԓ��m�̎���
��Q�҂͕Ў���������ǂ�
�ߎ�����
| ��Q�� | 10�� |
|---|---|
| ���Q�� | 90�� |
��Q��35�Βj����Ј��Ō���40���~
| ���̂ɂ��x�Ɗ��� | 11���� |
|---|---|
| ���@ | 280�� |
| �ʉ@ | 95�� |
�@�ϋɑ��Q�F���v�F425��9900�~
| ���ʉ@���Ô� | 210���~ |
|---|---|
| ���@�G�� | 42���~�i1,500�~�~280���j |
| �t�Y�Ō�� | 170���~�i�E�ƕt�Y150���~�A�ߐe�ҕt�Y20���~�j |
| ���ʉ@��ʔ� | 3��9900�~ |
�A���ɑ��Q�F���v�F6432��3838���~
| �x�Ƒ��Q | 440���~������40���~�x�Ɗ���11�J�� |
|---|---|
| �편���v | ����Q����5���ŘJ���\�͑r������79�� |
��Q�҂�35�Ȃ̂ŏA�J�\�N����67�܂ł�32�N��
���C�v�j�b�c�W����15.8027��40���~�~11�J���~0.79�~15.8027��5992��3838�~
�B�Ԏӗ��F���v1780���~
| ���ʉ@�Ԏӗ� | ���@�Ԏӗ��Z��\����196���~�`312���~�͈̔͂ƂȂ�A280���~�Řb���������� |
|---|---|
| ���LjԎӗ� | 1500���~�Řb���������� |
�w���Q�����z�x���@+�A+�B�~�i100-��Q�҉ߎ������j��100
��8638��3738�~�~90��100���V�V�V�S���T�R�U�S�~
�A���A���̗�ٌ͕�m�Ɉ˗����������ŕٌ�m���ŎZ�o���Ă��܂��B
�R�̎x������̒��ł͈�ԍ��z�ƂȂ�v�Z�ł��B
5-1 ����Q�̔����z�̌v�Z��`�ٌ�m�Ɉ˗����Ȃ��ꍇ
����̕ی���Ђ͕ی���Ђ̎x������ŎZ�o���܂��B
��������Ⴂ���z����Ă������ɂȂ�܂��B
�܂��A���ɂ͕ی���Њ�����Ⴂ���z����Ă���ꍇ������܂��B
������Ǝ�����Y���Ďx����������ƂɎZ�o���������ȑ��Q�����z����Č����ĉ������B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�܂��͎����ŕٌ�m����p���Čv�Z���Ă݂܂��傤�I
�����āA�ی���Ђ��ǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă��邩���A��r���Ă݂ĉ������B
�E�����Ō�����ꍇ�̑��Q�����z�̑���́H�ٌ�m���z��70�`80��
�ٌ�m���ŎZ�o�����z��70�`80�����x�̋��z�ł���Ύ��k�ɉ�����͈͂ł͂���܂��B
�������������Ō����s�����A�ٌ�m�Ɉ˗�����A�ٌ�m���̌v�Z�ɉ����Ă����\��������܂��B
�������A�i�ȊO�̎��k���ł́A��Q�ґ����������ċύt��}��K�v������܂��B
���������ٌ�m���ł̑��Q�����z������Ƃ͌���܂����B
�܂�A�o���̒z�̍����Q�C�R���Ȃǂ̏ꍇ�A���Ԃ�����܂ŏ�������Ȃǂ��l���Ȃ��Ă͂����܂���B
�܂��A���ǂ��c��悤�Ȏ��̂ł͑��Q�����z�����z�ƂȂ�A������ł͍ŏI�z�ɑ傫�ȊJ�����ł܂��B
�d�x�̌��ǂō��z�ƂȂ�ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�Ɉ˗������ق������z�Ȑ������\�ƂȂ�܂��̂ň˗����������Ă݂ĉ������B
���̏ꍇ�A�ٌ�m��p���C�ɂȂ�Ƃ���ł����A���ۂɂٌ͕�m��p�����������Ă��˗������ق��������̎茳�ɂ��邨���������Ȃ�P�[�X����������܂��B
�܂��A�P�[�X�ɂ���Čv�Z���قȂ邽�ߓ����������A���߂ǂ��̔��f������A�d����Q���ď����̉���p�̐���������ꍇ�ɂ́A�ٌ�m�ȂǂɈ�x���k���邱�Ƃ������߂��܂��B
����Q���c��P�[�X�̑��Q���������`�������ڂƎZ�o���@